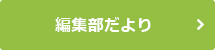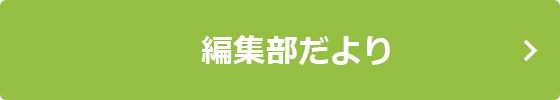2019.12.13野鳥写真家・和田剛一さんと"空飛ぶ川漁師"ミサゴの「落ちアユ漁」を見に行ってきた

12月1日に「落ちアユ漁」が解禁になった仁淀川。産卵のためにアユたちが下ってくる、河口から近い、いの町や土佐市の仁淀川には例年解禁を待ちわびていた多くの太公望たちが繰り出します。じつはこの時季を心待ちにしていたのは人間たちだけでなく野鳥たちも同じ。産卵場の周囲では魚を主食にする大型の野鳥たちも落ちアユ漁に沸き立っているであろうという予想をたてて、高知市土佐山在住の野鳥写真家・和田剛一さんと一緒に人と野鳥たちの「落ちアユ漁」を見に行くことにしました。
 仁淀川漁協が整備したアユの産卵場を見渡せる堤防の上でカメラを構えて観察する和田剛一さん。
仁淀川漁協が整備したアユの産卵場を見渡せる堤防の上でカメラを構えて観察する和田剛一さん。今回の「落ちアユ漁ウォッチング」の現場は、仁淀川漁業協同組合やアユ釣り愛好家たちが川床を整備したアユの人工産卵場。ここは禁漁区に指定されているので人間たちは立ち入り禁止、だから野鳥たちは安心して漁に励めるはずと予想を立てたのだが…。行ってみると産卵場には鳥除けのための細いロープやテグスが水面すれすれに何本も張られている。アユたちの産卵を鳥たちから守るために漁協が張り巡らせたものだ。鳥たちはこの障害物を除けながら漁をしなければいけない。なんとなく気の毒な気がするのだが、ここはアユたちの繁殖活動を促して来年の遡上を確保するために人手と費用をかけて整備した産卵場。鳥たちはアユを捕食する害鳥なんだからしょうがないですかね(笑い)。
 人工的に作られたアユの産卵床は高知自動車道の橋のすぐ下流、いの町八田にある。(撮影/和田剛一)
人工的に作られたアユの産卵床は高知自動車道の橋のすぐ下流、いの町八田にある。(撮影/和田剛一)
さて。今回の落ちアユ漁ウォッチングのターゲットはミサゴという野鳥。
猛禽類(ワシタカ類)の仲間で、生きた魚を捕食することから「魚鷹(うおたか)」の別名がある。空中でホバリングして水中の魚に狙いを定めて急降下し、両足を使って魚を捕まえるスタイルが超カッコいい、私が大好きな野鳥だ。英語名はオスプレイ、じつはあの評判の悪い戦闘機の名前はここからきています。ミサゴに何の罪もないんですが、ちょっと可哀想ですね(笑い)。
アユは河床に小さな玉砂利が敷き詰められたような浅い瀬を選んで産卵します。本来は自然の状態でそういう場所があちこちにあればいいのですが、川が荒れて最近は少なくなってきているので漁協やアユ釣り師たちが中心になって産卵床を人工的に作って応援しているというわけです。
人工産卵床作りは、緩い流れのある浅瀬に最初にユンボなどの機械を入れて、人が動かせない大石などを取り除き、そのあとに人海戦術で人が鍬を入れて川床を耕します。こうすることで堆積した泥や細かな砂を流して玉石だけを残し、同時に硬くなった川床を柔らかくする。アユたちは産卵するときに尾びれを振りながら川床を掘り上げて卵を石に付着させるので、産卵をするときに小石が動きやすいように鍬で耕すのです。高知県では仁淀川のほかにも新荘(しんじょう)川、鏡川、物部(ものべ)川、安田川、奈半利(なはり)川でも同じような方式で人工的産卵床の整備が行われていて実際に成果が出ているといいます。
▼2017.11.24のコラム
<川遊び人の独り言>4 アユの産卵~命のバトンタッチの現場では~
 これは天然の産卵床。浅い瀬に小石と大きめの砂が川床にびっしり散らばっていて大きな石はない。
これは天然の産卵床。浅い瀬に小石と大きめの砂が川床にびっしり散らばっていて大きな石はない。いの町八田堰下流に作られた産卵場に着いてみると、いるいる! 落ちアユ狙いの大型の野鳥たちがたくさん集結しています。まず目立つのは真っ白いボディのダイサギたちの群れ。産卵場にズカズカ入り込んで足下に寄ってくるアユたちを狙っています。やや大型で青みががった灰色の羽根のアオサギも混じっているのが確認できます。
 産卵場に集まったダイサギの群れ。(撮影/和田剛一)
産卵場に集まったダイサギの群れ。(撮影/和田剛一)上空を見上げるとトンビ(鳶)の群れがぐるぐると旋回しています。和田さんは堤防の上に停めた車の運転席から周囲をぐるりと見まわしたあと、ドアを静かに開け、ゆっくりとした動作で降りたちます。鳥は車そのものにはそれほど警戒しないが外に出てくる人に対しては急に警戒心が高まる、と和田さん。上空を見まわし、次に眼下に広がる仁淀川の河原全体を観察してミサゴを探します。「飛んでるやつはいませんが、河原に4羽、遠くの電線に2羽いますね。ほら、産卵場に立てられた棒杭にも1羽とまってますよ」と和田さん。確かに棒杭には大型の猛禽らしき鳥が羽を休めています。双眼鏡片手にあちこち目を凝らす私の横で、双眼鏡なしであっという間に目指す野鳥を見つけてしまう和田さんのプロの眼には驚くほかない。
 棒杭にとまって休んでいるミサゴ。(撮影/和田剛一)
棒杭にとまって休んでいるミサゴ。(撮影/和田剛一) 和田さんの目にはこの電線にとまっている鳥の中にミサゴが見えるらしい。私には確認できなかった。(撮影/和田剛一)
和田さんの目にはこの電線にとまっている鳥の中にミサゴが見えるらしい。私には確認できなかった。(撮影/和田剛一)「どうしてそんなに早く見つけられるんですか?」
「うーん、長年野鳥を相手にしてきた皮膚感覚かなあ。それでも最近は歳とって目が悪くなったので能力はガタ落ちですよ」
と古希を迎えたばかりの和田さんは嘆くが、ハンパない眼力だなあ。そんな話をしながら、空中からダイビングする写真を撮りたくて産卵場を見下ろす堤防の上でしばらく待ち続けたが、河原のミサゴたちが飛び立つ気配はなく、電線から飛来するものもいない。「朝の食事を終えて休んでいるところですね。お腹が空いたらまた狩りをはじめると思うんだけどねえ」と和田さん。
とりあえずもっと下流を見に行くことにしました。
 河原に多数の車が停まっている落ちアユ漁の現場。(撮影/和田剛一)
河原に多数の車が停まっている落ちアユ漁の現場。(撮影/和田剛一)車を下流に向かって走らせていると仁淀川河口から上流に向かって2本目の橋、国道56号線に架かる仁淀川大橋のすぐ下流の広い河原にたくさんの車が停まっているのを見つけた。川の中に立ちこんでたくさんの人たちが動き回っています。

 オモリの付いた掛けバリ仕掛けを川床にギリギリに転がし、集まった落ちアユを引っ掛けるコロガシ漁を楽しむ釣り人。(撮影/和田剛一)
オモリの付いた掛けバリ仕掛けを川床にギリギリに転がし、集まった落ちアユを引っ掛けるコロガシ漁を楽しむ釣り人。(撮影/和田剛一)さっそく河原に降りて行ってみると、漁の現場は活気づいていた。天然の産卵場となっている浅い瀬(ここは禁漁区になっていない)に集まった落ちアユを狙って年配の太公望たちが(この日は平日だったのでたぶん定年退職組)胸までの長靴を履いて忙しく動き回っています。落ちアユ漁の人たちです。アユ釣り師の端くれにいる私もなんだが心が騒ぎますね(笑い)。
 刺し網に掛かった落ちアユを網から外しているところ。「今年の調子は?」と聞くと「まあまあやないの」という答えが返ってきた。
刺し網に掛かった落ちアユを網から外しているところ。「今年の調子は?」と聞くと「まあまあやないの」という答えが返ってきた。 クーラーの中を覗いてみるとかなりの大漁。
クーラーの中を覗いてみるとかなりの大漁。 黒くてざらついたボディはこの時期のアユの特徴。夏の美しい姿のアユはもういない。ちょっと寂しい。
黒くてざらついたボディはこの時期のアユの特徴。夏の美しい姿のアユはもういない。ちょっと寂しい。 落ちアユ漁の人たちを撮影していた和田さんが突然声を上げました。
「あっ、飛んでますよミサゴが」と指さす上空には大型の鳥が2羽、ゆっくりと旋回しています。大きさはトンビと同じくらいだが、羽ばたきを繰り返しながら飛ぶところが明らかに違うし、尾羽の形もちがう。下から見上げるボディは白く、目の端から首にかけて黒いオビがある。「魚鷹」の名前にふさわしい風格のようなものが感じられる(トンビには申し訳ないが)。和田さんは望遠レンズで、私は双眼鏡でミサゴを追いかけるが、上空を旋回するだけでなかなかダイビングしない。落ちアユ漁を楽しむ人間たちを警戒しているようです。
この場所で1時間くらい粘りましたが、ダイビングする気配がないので撮影をあきらめて「そろそろお腹が空いてきているかもしれない」ということで最初の場所に戻ることにしました。ふたたび八田堰下流の人工産卵場を見下ろす堤防上で待つこと20分余り、ついに上空にミサゴが姿を現わしました。ゆっくり旋回しながら徐々に高度を下げて産卵場に近づき、水面すれすれで足を水中に突っ込んだかと思うと、突然水しぶきが上がり、何かをワシづかみにして上空へふたたび飛び上がりました。
「あっ、落ちアユ漁成功!アユをしっかり掴んでますよ!」と和田さんが叫びましたが、双眼鏡で見ていた私には何が起きたのかよくわかりませんでした。しかし、和田さんのカメラのモニターを覗いて初めて何が起きていたのかがわかりました。
ご覧いただきましょう、下の写真がその瞬間をとらえたものです。日本を代表する野鳥写真家、和田剛一さん、さすがのスーパーショットです。
 ミサゴが水中のアユを文字通りワシ掴みした瞬間。(撮影/和田剛一)
ミサゴが水中のアユを文字通りワシ掴みした瞬間。(撮影/和田剛一)関係者によると仁淀川下流域でのアユの産卵行動は12月下旬くらいまでは続くとのことなので、ミサゴの落ちアユ漁を見るチャンスはまだまだあると思われます。週末は双眼鏡片手に仁淀川の八田堰周辺の散歩にぜひお出かけください。
★次回の配信は12月20日予定。
次回はアンコールシリーズ。2017.10.27配信の”仁淀ブルーに誘われて~私の高知移住日記 『自転車編』”と、「その後の近況」をお届けします。
お楽しみに!
(野鳥好きの仁淀ブルー通信編集長・黒笹慈幾)
●今回の編集後記はこちら