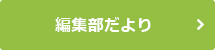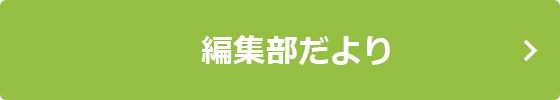2018.11.16四国一の秘境の神社かも!?

仁淀川流域はガチな秘境だらけですが、心がざわめくほどの感動を与えてくれる秘境といえばこの聖神社。この秋ぜひ訪れてほしいディープな観光スポットを紹介します。
仁淀川流域6市町村の観光情報サイトには魅力的な旅のスポットがいくつも紹介されていますが、そのなかで個人的に気になっていたのが聖神社(越知町)。名所として紹介されているものの、
・山や木で衛星の電波が遮られ、スマホのGPS(位置情報)機能が不安定になるらしい!
・かなりの山奥で道路は狭く、大雨やそのあとは土砂災害の可能性が!
しかしこのところ涼しくなって、虫は少ないし天候も安定しているので、ついに行ってきました。
 聖神社へはこの緑色の案内板が導いてくれる。ただ、ご覧のとおりあまり大きくない案内板なので見落とさないように。
聖神社へはこの緑色の案内板が導いてくれる。ただ、ご覧のとおりあまり大きくない案内板なので見落とさないように。聖神社へは、越知市街の国道33号から越知橋のたもとで県道18号に入ります。桐見ダムを過ぎてしばらくは道なりですが、上の画像のような案内板が見えたらそちらの道へ。
 聖神社入口の駐車スペース(乗用車5台ぐらい駐車可)。
聖神社入口の駐車スペース(乗用車5台ぐらい駐車可)。 聖神社対岸入口。
聖神社対岸入口。 聖神社への入り口は2ヶ所。『聖神社対岸入口』は聖神社を展望できる場所をへて聖神社へ。『聖神社』という看板があるほうの入り口はまっすぐ聖神社へ。
まずは遠目に神社を眺めて「あそこを目指すのだ!」のほうが盛り上がるだろうと、『聖神社対岸入口』からのルートを選びました。
が、この山道、けっこうハード。
 聖神社対岸入口からの山道は、登山経験が浅い人には迷いやすいかも。
聖神社対岸入口からの山道は、登山経験が浅い人には迷いやすいかも。登り口からかれこれ13分で展望所に到着しましたが、11月だというのに汗だくです。でも苦労に見合う絶景が。
 この岩壁に、この岩穴に、このお堂を建てることにした人間の創造性に感動(いや、その執念に慄きか)。
この岩壁に、この岩穴に、このお堂を建てることにした人間の創造性に感動(いや、その執念に慄きか)。 いつ、なぜあんな所に神社を築いたのか?
少なくとも明治11年(1878年)には存在したそうですが、それ以前の歴史ははっきりせず、おそらく江戸時代後期に建立されたとのこと。鳥取県の三徳山にある『投入堂(平安時代後期建立で国宝)』と同じような立地と形態のため、『土佐の投入堂』とも呼ばれています。『投入堂』とは、法力で仏堂を崖に「投げ入れた」という言い伝えにちなんだもの。
 緑の魔境とでもいうべきディープな大自然のなかにある聖神社。
緑の魔境とでもいうべきディープな大自然のなかにある聖神社。ここからは急な山肌を横切り、谷を渡って下っていきます。登山経験がない人には怖い道かもしれません。
 向きが少々正確でない道案内標識もある。展望所にあるこの標識では、「帰り道」と表記してあるほうの道(画像の中心よりやや左上奥に続く道)が聖神社へのルート。
向きが少々正確でない道案内標識もある。展望所にあるこの標識では、「帰り道」と表記してあるほうの道(画像の中心よりやや左上奥に続く道)が聖神社へのルート。 ロープにつかまって横断する急な斜面もある。
ロープにつかまって横断する急な斜面もある。 ゴツゴツした岩場を下っていく。
ゴツゴツした岩場を下っていく。 ロープを頼りにしないと下りられないところも。
ロープを頼りにしないと下りられないところも。 ぐらぐらする吊り橋からの眺め。
ぐらぐらする吊り橋からの眺め。そして、いかにも修験者が打たれたであろう滝があらわれ、目の前にはやや傾いていてぐらぐら揺れる吊り橋が……
 揺れるけど、ここからの渓谷の眺めは素晴らしい。
揺れるけど、ここからの渓谷の眺めは素晴らしい。吊り橋の先はなんと洞窟へ! 小さな照明があるけれどほぼ闇です。私は登山家の端くれなのでどんな山にもヘッドランプを持参するのですが、それが役立ちました。
 「橋の先が穴」という目を疑う光景が。洞窟は意外と長いです。
「橋の先が穴」という目を疑う光景が。洞窟は意外と長いです。 なんなんだ、この洞窟は……
すると出口に説明板が。マンガン(乾電池や合金の材料)という鉱石を採掘した跡らしい。ちなみこの谷の上流にはさらにたくさんの坑道や精錬場跡などがあり、昭和15~25年ごろにはたくさんの鉱山労働者がいたという話も。いまは深い森ですが、ここには一体どんな暮らしや繁栄があったのでしょうか。
 聖神社への道は、越知町の有志や地域おこし協力隊が整備してくれています。
聖神社への道は、越知町の有志や地域おこし協力隊が整備してくれています。洞窟を出ると、聖神社への登りが始まります。急斜面ですが、鎖や木製のハシゴが助けてくれます。そしてついに聖神社へ。
 全体像をカメラに収めるのが難しいぐらい崖に建っています。
全体像をカメラに収めるのが難しいぐらい崖に建っています。聖神社は屋根が崩れたり床が落ちたりと崩壊寸前でしたが、1988年に越知町の岡村豊延さんが修復を開始。ときには奥さんも手伝って命がけの作業をしたそうです。
 ここに籠り、修験者たちはどんな修業をしたのだろうか……。
ここに籠り、修験者たちはどんな修業をしたのだろうか……。 山肌に乗っかっているだけなんですね……。
山肌に乗っかっているだけなんですね……。お堂からの眺めは、絶景という言葉ではたりない何かがありました。大自然に抱かれるというより、とらわれるという感じ。懐かしい人も風景もはるか彼方――世界から切り離されたような寂しさや喪失を強く感じさせる場所です。しかし安らぎもある。このお堂を築いた人の強い意志がいまも宿り、訪れる人の心を支えるのでしょうか。ここで静かに時を過ごせば、素の自分になれる気がしました。
 苔むした渓谷に癒されながら神社を後にした。
苔むした渓谷に癒されながら神社を後にした。下山はもう一つの入り口(聖神社の看板あり)のほうへ。これまでの難路を思い出して、「先が思いやられる」と覚悟していたら、あっけなく下山。登山や体力に自信がない人は、聖神社の看板からの参拝がおすすめです。でも、『聖神社対岸入口』からだとプチ冒険的でインスタ映えしますよ~。
 洞窟や吊り橋へは、「聖神社」の看板のほうの入り口からが近い(約15分)
洞窟や吊り橋へは、「聖神社」の看板のほうの入り口からが近い(約15分) 「聖神社」の看板のほうの入り口。
「聖神社」の看板のほうの入り口。●聖神社参拝コースタイム
聖神社対岸入口
↓(15分)
展望所
↓(20分)
吊り橋・洞窟
↓(10分)
聖神社
↓(10分)
聖神社の看板がある入り口
聖神社(越知町ホームページ)
(仁淀ブルー通信編集部/大村嘉正)
●今回の編集後記はこちら