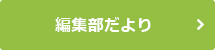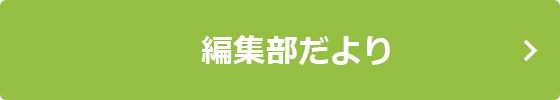2017.10.20「仁淀川いきものがたり」サワガニの不思議

仁淀川の上流や支流には、どこでも当たり前のように生息しているサワガニ。川沿いの家には時々遊びに来たりもする。サワガニが家に遊びに来るなんて、うらやましいなあ。
どこにでもいるけど、実はここだけ?
サワガニはほぼ日本中に生息する、ごく普通の淡水のカニだ。
川の上流域や湧水などが流れる小川に生息している。地域によっては食材として売られていたり、居酒屋や小料理屋さんなどでは一品料理で出ることも。
でも実は、このサワガニは日本固有種で、日本でしか見られないカニなのだ。


夜行性というわけではないが、日中は、あまり行動せず、夜になると活発に動き回っている。
基本的には水辺の生き物で、水から上がり、陸地でも見かけることは多い。雑食で、枯葉も食べれば、虫や魚の死体も食べる。寿命は長く10年ほど生きると言われている。


川に住む甲殻類、カニやエビの仲間は、繁殖するために、どうしても一度海に下らなければならない(エビの種類には一部淡水で増えるものもいる)。海で卵から生まれて幼生で育ち、川へ上っていく。淡水魚の仲間でも海で育ち川を上るものは多い。本来はすべての川の生き物がそうだったといわれている。
幼生って何かっていうと、たとえば、しらすのパックを買うとトゲトゲのプランクトンみたいなのが入ってることがあるよね。その大半が海のカニやエビの幼生。幼生は海で育ちながら何回か形を変えて親と同じ形になって成長していくんだ。
だから、川と海がストレートにつながっている場所では生き物が多く、ダムや堰がある川では少ないことになる。
生れた時からオトナだよ
ところがこのサワガニは、日本にいるカニの中で、海に下らず川だけで生活する唯一のカニなのだ。「海で育つ」と言う部分がない。川で生まれて川で育つ。
そして卵が大きく、その卵から生まれる子供は他のエビやカニと違い、幼生ではなく、最初からカニの姿をしている。
小さな赤ちゃんガニはしばらく親にくっついていて、ある程度成長すると、親から離れて単独で行動するようになる。
他の例でいうと、アメリカザリガニが同じような赤ちゃんの産み方をする。




 カニは寒くなると、暖かくなるまで寝て過ごす。川の河口付近にいる多様なカニも同じだ。越冬場所は様々で、水から上がり、水辺の石や、くち木などの下に穴を掘り寝ている。驚いたことに、水辺から数十メートル離れた雑木林で見つけたこともある。乾燥さえしなければ、水辺から離れていても越冬するようだ。
カニは寒くなると、暖かくなるまで寝て過ごす。川の河口付近にいる多様なカニも同じだ。越冬場所は様々で、水から上がり、水辺の石や、くち木などの下に穴を掘り寝ている。驚いたことに、水辺から数十メートル離れた雑木林で見つけたこともある。乾燥さえしなければ、水辺から離れていても越冬するようだ。サワガニの色は何色?
さて、同じ生き物でも、体色の違う個体がいるが、それはとても珍しいことで、あまり目にすることはない。ところがこのサワガニは違う。
黒っぽい甲羅にオレンジ色の足が普通だと思う人もいれば、場所によって、甲羅が茶色や水色のサワガニがいる。いつも黒い甲羅にオレンジ色の足のサワガニを見ている人が、水色のサワガニを見るとびっくりする。逆に、水色のサワガニしかいない場所もあり、それしか知らない人にとっては他の色が珍しく思われる。
仁淀川で見たサワガニは黒甲羅にオレンジ足がほとんどだったが、茶色の甲羅も見つけた。もしかしたら四国の他の川には違う色が見つかるのかもしれない。
 水色のサワガニ。私は東京に住んでいるが、近くで見るサワガニは、黒甲羅にオレンジ色の足なので、伊豆の山で初めてこの水色を見たときは大発見! と騒いだものだ。でもそれはカラ騒ぎだった。どこにでもいることがわかり、肩を落とした。
水色のサワガニ。私は東京に住んでいるが、近くで見るサワガニは、黒甲羅にオレンジ色の足なので、伊豆の山で初めてこの水色を見たときは大発見! と騒いだものだ。でもそれはカラ騒ぎだった。どこにでもいることがわかり、肩を落とした。 なぜ色の違うサワガニがいるのかはよくわからない。自分なりにあちこちの川でサワガニを見てきて、最初は海に近い川や、海に直接繋がっている川に水色のサワガニがいるのだと思っていたのだが、そうではなさそうだ。
地域差、地質の違い、などの説もあるが、同じ川で混在しているところを見ると、餌や周辺環境の理由じゃないような気もする。
色々な人が色々な角度で調べているが、現時点で有力な説は、遺伝子の違いがそのまま継続しているんじゃないかということだ。それにしても黒と茶色と水色が混ざりあった個体のないのが不思議だが、まだはっきりしたことは解明されていないようだ。
どこでも目にする普通のサワガニでもこのように、はっきりとわかっていないことがあるなんて、とても面白い。自然界にはまだまだ謎がたくさん隠れている。ちょっと観察する目で見れば色々な生き物で不思議なところは見つかる。それを自己流で、調べていくのも生き物観察の面白いところだ。
奥山英治(日本野生生物研究所)
●今回の編集後記はこちら