2016.07.22天然ウナギは、もう釣ってはいけない?

『仁淀川資源調査研究所』から(3) ウナギ釣りが大好きな方々。これから私が書くことを心して読んでください。いやはや、たいへんな時代になったものですよ。
小学館発行の大人の生活誌『サライ』8月号で、ウナギ特集の取材を仰せつかりました。雑誌のウナギ特集といえば土用丑の日に向けたお約束的企画ですが、8月号のサライ、それまでの食情報企画とはまったく趣きが違います。
その号の顔ともいうべきサライ・インタビューは、世界で初めてニホンウナギの卵を採取し(世界19種・亜種のウナギ属魚類でも初めて)、長年謎だったその産卵場所を太平洋西マリアナ海域と特定した塚本勝巳さん(現・日本大学ウナギ学研究室)。
ウナギ特集巻頭の解説記事は、塚本さんとともに世界のウナギ属魚類を研究してきた東京大学大気海洋研究所の青山潤さんです。
ウナギは深海魚から進化した魚で、ニホンウナギの仔魚が数千キロもの旅を経て日本列島の河口へ到達するメカニズムは、気候や海流などさまざまな要素が偶然重なりあって完成した、奇跡のような仕組みなのだそうです。
卵が発見されるまでの苦労が示すように、海域におけるウナギの生態解明はまだ始まったばかり。ところが、ニホンウナギの資源量そのものはこの半世紀でおよそ10分の1にまで減っており、国際自然保護連合は一昨年、絶滅危惧種としてレッドデータリストに記載しました。
私たちはウナギとどのように付き合っていけばよいのか。その問いかけを引き取る形で率直な意見を述べてくれたのは、東京・東麻布にある鰻料理の老舗『野田岩』5代目の金本兼次郎さんです。
野田岩といえば、天然ウナギを食べることのできる東京でも今や珍しい店。「肝焼きに釣針が入っていることがありますのでお気をつけください」という箸袋の一文でも有名です。ところが、天然もので名を売ってきた名店の主は「もう天然ウナギは扱えなくなってもいい」とおっしゃるではありませんか。
仕事として成り立つほど漁獲がないため、この数十年、ウナギ漁師は全国的に減り続けてきたそうですが、とくに関東の場合、2011年に起きた東日本大震災の原発事故を機に廃業する川漁師が続出。単価の高騰だけでなく集荷効率も悪くなる一方で、もはや天然ウナギの値段は顧客に転嫁できる限度を超えてしまっているといいます。
一方、養殖ウナギの品質は、志の高い業者のものに関しては非常によくなっており、十分客の舌を満足させることができる水準だとか。野田岩が扱っている8割近くも養殖ウナギです。
養殖とはいえ、その種苗は元をただせば西マリアナ生まれの野生魚です。ウナギの完全養殖技術は近年急速に研究が進んでいますが、まだ採算にあうところには達していないそうです。
天然物であれ養殖物であれ、今までのように漫然と食べることの許されない空気が、ウナギを取り巻く現場にひしひしと忍び寄っている感じがしました。
今回の特集で取り上げたのは、1匹1匹を大切に扱い、最高の状態で提供することを誇りにしてきた店。長い時間待つだけの価値がある丁寧な仕事を続けてきた専門店です。
 このうな丼は川漁師さんの天然もの。鰻料理はもともと流域の文化。孫たちの時代までも鰻の魅力を伝えたい。
このうな丼は川漁師さんの天然もの。鰻料理はもともと流域の文化。孫たちの時代までも鰻の魅力を伝えたい。近年、蒲焼きはスーパー、コンビニ、ファストフード店などでも気軽に食べることができるようになりましたが、ウナギという野生魚を減少に追い込んできたのは、まさにこの価格破壊≒大量消費という経済構造です。
今や狂騒と化した熱気が沸点に達するのが、間もなく訪れる夏の土用丑の日。野田岩の金本さんは、東京の鰻専門店がこの日一斉に休むだけでも鎮静効果が生まれ、ウナギの相場は健全化するだろうとおっしゃいます。ちなみに野田岩本店は土用丑の日は休業です。理由は「忙しすぎると職人の手が雑になる」からだとか。
専門家の間では、養殖用のシラスウナギに漁獲規制をかけるだけでは不十分で、川に棲息する親ウナギの捕獲も制限し、保護をはかる必要があるという声が大きくなりつつあります。
仕事としての漁であろうが、遊びの釣りであろうが、もう親ウナギは獲物として狙うべきではないというのが生態学者たちの総意らしいのです。県によっては、産卵に向かう秋の下りウナギを保護するため一定の禁漁期間を設けるところも出てきました。
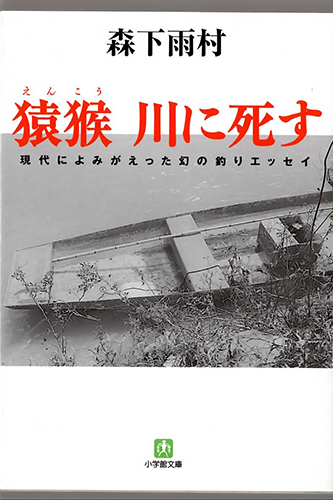 佐川町が生んだ作家、森下雨村の『猿猴 川に死す』『釣りは天国』(小学館文庫版)
佐川町が生んだ作家、森下雨村の『猿猴 川に死す』『釣りは天国』(小学館文庫版)仁淀川は昔からウナギの多い川で知られ、森下雨村の『猿猴 川に死す』に登場する「ひご釣り」の描写などは、何度読んでも胸躍る興奮があります。仁淀川は今でも全国のほかの川よりウナギの棲息密度が濃い印象がありますが、今後もウナギを清流のシンボルのひとつに掲げていくのであれば、なんらかの取り組みや積極的な意思を、流域として示していく必要があると感じています。
(仁淀川資源研究所所長 かくまつとむ)
●今回の編集後記はこちら




















