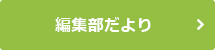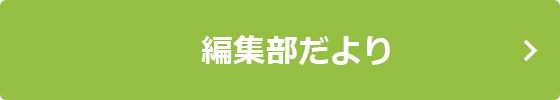2015.08.11仁淀川の夏の風物詩、「夏鮎」を目と胃袋で楽しみませんか

夏の仁淀川の風物詩と言えば、清冽な仁淀のブルーの清流とその中に立ち込み、川の風景と一体となって長竿を振るたくさんの釣り人の姿ですね。彼らはいったい何をどのようなやり方で釣っているのか疑問に思ったことはありませんか。
釣り人を夢中にさせているのは、春に河口から遡上(さかのぼること)し、仁淀川ブルーの水で育ったミズゴケ(珪藻や藍藻類)を食べて大きく立派に成長した鮎(アユ)です。この時期のアユを釣るには友釣り(ともづり)という日本だけの伝統的な釣法があります。
鮎は水中の石についたミズゴケを、独特の形をした顎と口を使って器用に削り取りますが、いいミズゴケのついた場所を自分の縄張りとして死守する習性があり、他の鮎が侵入してくると猛然と追い払います。その習性を利用した釣りが「友釣り」です。
「友釣り」はオトリの鮎を水中に泳がせ、そこに攻撃を仕掛けてくる野鮎(のあゆ)をハリに引っ掛けて釣り上げる豪快な釣りスタイルです。野鮎が掛かると竿にはオトリ鮎と野鮎の2尾分の重量がかかってくるので大きくしなり、激流の中でそれを取り込もうとする釣り人との緊迫したやり取りが始まります。これが友釣りの醍醐味で、釣り人を夢中にさせる理由です。また、鮎の習性をうまく利用した知的でしかもエキサイティングなハンティング技術とも言えます。
鮎は年魚(ねんぎょ)といって1年で一生を終える魚です。秋に河口近くの瀬で産み落とされた卵は平均2週間ほどで孵化し稚魚はそのまま海にくだり、冬の間は岸近くの浅い海で過ごし、翌春、水温がおおむね10度Cを越えるようになると再び川に戻ってきて上流に向けて遡上(さかのぼること)し始めるといわれています。このときの体長は5~10cmくらいですが、上流でミズゴケをたっぷりと食べた鮎はみるみる大きくなり、8月に入ると25cmを越える大型も出始めます。
清冽な仁淀ブルーのミズゴケを食べて育った仁淀川の鮎は食味も素晴らしく、釣り人が友釣りで釣った一本釣り(こういう表現が適切かどうかわかりませんが)の鮎は、翌日の朝1便の飛行機で高知空港を発ち、その日の夜に東京の鮎料理専門店で提供されて大好評を博しています。
もちろんこの時期は、高知市内や流域の飲食店でも仁淀川の鮎を食べることができます。
7月下旬から8月中旬に水揚げされる鮎は脂が乗り、一年で一番おいしいと私は思います。釣りをやらない人も、ぜひ一度この時期の仁淀川の「夏鮎」をご賞味ください。
(釣りバカ編集長 黒笹慈幾)
●今回の編集後記はこちら
◆仁淀川の友釣り鮎が食べられる東京の店
「新ばし鮎正(あゆまさ)」http://ayumasa.main.jp/
〒105-0004 東京都港区新橋4-21-14 TEL:03-3431-7448◆ふるさと納税(越知町)のお礼品として
仁淀川の友釣りの鮎がいただけることで目下、大人気のサイト
「ふるさとチョイス」http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/39403
 空の青を映す夏の仁淀川の流れ。水も山も空も夏の顔をしています。越知町鎌井田地区。
空の青を映す夏の仁淀川の流れ。水も山も空も夏の顔をしています。越知町鎌井田地区。 掛かったばかりの夏鮎。胸に楕円の黄色いマーク(追い星という)、尻ビレの先の鮮やかな黄色の縁どりが野生鮎の証し。
掛かったばかりの夏鮎。胸に楕円の黄色いマーク(追い星という)、尻ビレの先の鮮やかな黄色の縁どりが野生鮎の証し。 鮎の友釣りをする釣り人はこんな道具を使います。奥は掛かった鮎をストックしておく「オトリ缶」、手前は鮎を活かしたまま運ぶ「引き舟」で、腰に付けて携行します。
鮎の友釣りをする釣り人はこんな道具を使います。奥は掛かった鮎をストックしておく「オトリ缶」、手前は鮎を活かしたまま運ぶ「引き舟」で、腰に付けて携行します。 流れに立ち込んで長い竿を振る釣り人は夏の仁淀川の風物詩。鮎釣り師が数多く集まる越知町黒瀬地区。
流れに立ち込んで長い竿を振る釣り人は夏の仁淀川の風物詩。鮎釣り師が数多く集まる越知町黒瀬地区。 越知町鎌井田地区の浅尾沈下橋の遠望。バワーのある瀬に大鮎が潜む私の大好きな釣り場のひとつです。
越知町鎌井田地区の浅尾沈下橋の遠望。バワーのある瀬に大鮎が潜む私の大好きな釣り場のひとつです。 仁淀川河口に一番近い堰(せき)、いの町八田(はた)堰。下の動画を撮った場所です。
仁淀川河口に一番近い堰(せき)、いの町八田(はた)堰。下の動画を撮った場所です。